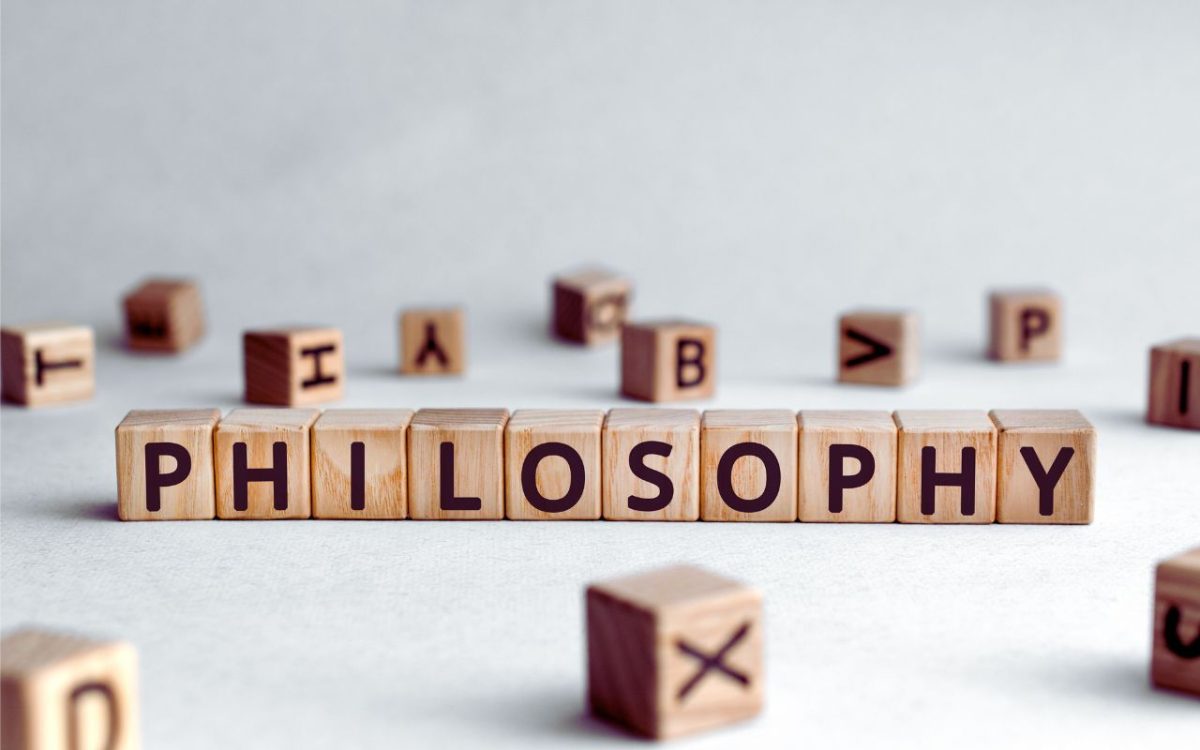
近年、企業経営において「経営理念」や「パーパス」「ビジョン・ミッション・バリュー(VMV)」といった言葉が多く使われるようになっています。しかし、これらの言葉の定義や役割について明確に整理されていない企業も多く、表面的な「理念風ワード」が社内にあふれ、形骸化しているケースも少なくありません。
この記事では、それぞれの言葉の本来の意味と役割をひもときながら、自社でどのように活用していくべきかを整理していきます。
経営理念とVMVの言葉の定義と役割
経営理念とVMV(ビジョン・ミッション・バリュー)は、企業の軸となる考え方を言語化したものであり、組織の方向性や行動基準を明確にするための指針です。
ここではまず、それぞれの言葉が何を意味し、どのような役割を果たすものなのかを整理していきます。
そもそもVMVとは何か?
VMVは、Vision(ビジョン)・Mission(ミッション)・Value(バリュー)の略称です。むすびでは、それぞれを以下のように定義しています。
- ビジョン(Vision):お客様と共に目指す未来
- ミッション(Mission):ビジョンを達成するために必要なこと
- バリュー(Value):どんな価値観・行動原則を大切にするのか」という指針
経営理念は何を伝えるべきものか?
経営理念とは、企業が社会に対してどういう存在でありたいか、何を大切にしているのかをまとめた根本的な価値観です。会社の創業精神や代表者の信念が反映されることが多く、長期的にぶれることのない“経営の軸”となるものです。
理念という言葉には明確な定義があるわけではなく、企業によっては「社是」「信条」「行動指針」といった形で表現されていることもあります。いずれにしても、社員や顧客がその会社の姿勢を理解するための「内なる羅針盤」として機能します。
言葉の定義よりも大切なのは「使い方」
実は、「理念」や「ビジョン」「ミッション」といった用語の定義には、学術的にも明確な区分はありません。企業ごとに微妙に異なる言葉で表現されていたとしても、それが組織の中で機能していれば問題はありません。
むしろ重要なのは、それらの言葉が「何を意図し、どのように使われているか」です。名称の正しさにこだわるあまり、本来果たすべき“意味”や“行動への影響”が失われては本末転倒です。
パーパスとSDGs文脈での再注目

最近では、「パーパス」という言葉が再び注目を集めています。これは単なる流行語ではなく、企業の存在意義や社会的責任を再定義する動きと深く関係しています。
アメリカで注目された「パーパス」という概念
「パーパス経営」が本格的に広まったきっかけのひとつとして考えられるのは、2019年、アメリカの「ビジネス・ラウンドテーブル(BRT)」です。この中で、長年アメリカの資本主義を支えてきた「株主第一主義」から脱却し、「すべてのステークホルダーに対する責任」を重視する方向へと舵を切るべきだと論理づけられたのだと思います。
この動きに呼応する形で、「企業は社会にどんな価値を提供するのか」「何のために存在しているのか」という問いが改めて注目されるようになり、「パーパス(Purpose)」という概念が脚光を浴びるようになったのです。
SDGsや社会的価値への関心の高まり
SDGs(持続可能な開発目標)への関心も世界中で高まり、企業に対して「経済的成果」だけでなく「社会的貢献」を求める動きが強まりました。こうした文脈において、パーパスは「社会的に果たすべき役割」を示す指針として、多くの企業が取り入れるようになっています。
日本では昔から「三方よし」や「公のために」という思想が企業経営に根づいており、その意味では“パーパス的な精神”は馴染みがあるとも言えます。
理念を変えずにパーパスを追加する企業が増えている理由
近年の傾向として、従来の経営理念を残したまま「パーパス」を新たに加える企業が増えています。背景には、すでに定着した理念体系を大幅に書き換えることのハードルが高いこと、また新しいステークホルダーへのアプローチが必要なことなどが挙げられます。
しかしこの動きが「流行に乗っただけ」のものになると、パーパスが単なるお飾りになってしまいかねません。本質は、既存の理念や行動と矛盾せずにどう組み込むかという点にあります。
本質は「呼び名」ではなく「機能」と「浸透」
理念体系を整理するうえで最も大切なのは、呼び名や言葉の正確さではなく、それがどのように組織の中で「機能しているか」「浸透しているか」です。
理念体系を定義することで組織がまとまる
理念やVMVをきちんと定義することで、組織の方向性が明確になり、社員が迷わず行動しやすくなります。経営層と現場の認識がズレていくと、企業の一体感は薄れ、パフォーマンスにも悪影響が出ます。
そのため、理念は“掲げて終わり”ではなく、事業計画や評価制度、日常のコミュニケーションにどう反映されるかが重要です。
形式にとらわれず、自社に合った言葉を選ぶ
「社是」でも「行動指針」でも「信条」でも構いません。大切なのは、自社が最も共感でき、行動に移しやすい言葉で表現されているかどうかです。
他社のフォーマットをそのままマネするのではなく、自社に合った理念体系を、自分たちの言葉で定義することが求められます。
社員にどう伝わり、どう行動に影響するかが要点
理念は“社内外へのメッセージ”であると同時に、“社員の行動”に直結するものです。形ばかり立派でも、社員が「自分の仕事とどう関係があるのか」がわからなければ、浸透はしません。
「行動と結びつく理念」であること。それが、経営理念やVMVの最大の存在意義です。
大切なのは言葉ではなく、その価値
「経営理念」「ビジョン・ミッション・バリュー」「パーパス」など、さまざまな言葉が組織の中で使われる時代において、大切なのは“名前の正しさ”ではありません。それぞれの言葉が何を意味し、どのように組織の中で使われ、行動や判断をどう導いているのか。
自社の文化や目指す方向に沿って、言葉を整理し、社員にとって意味のある理念体系を築くこと。それが、企業の持続的成長とブランド構築の第一歩です。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



