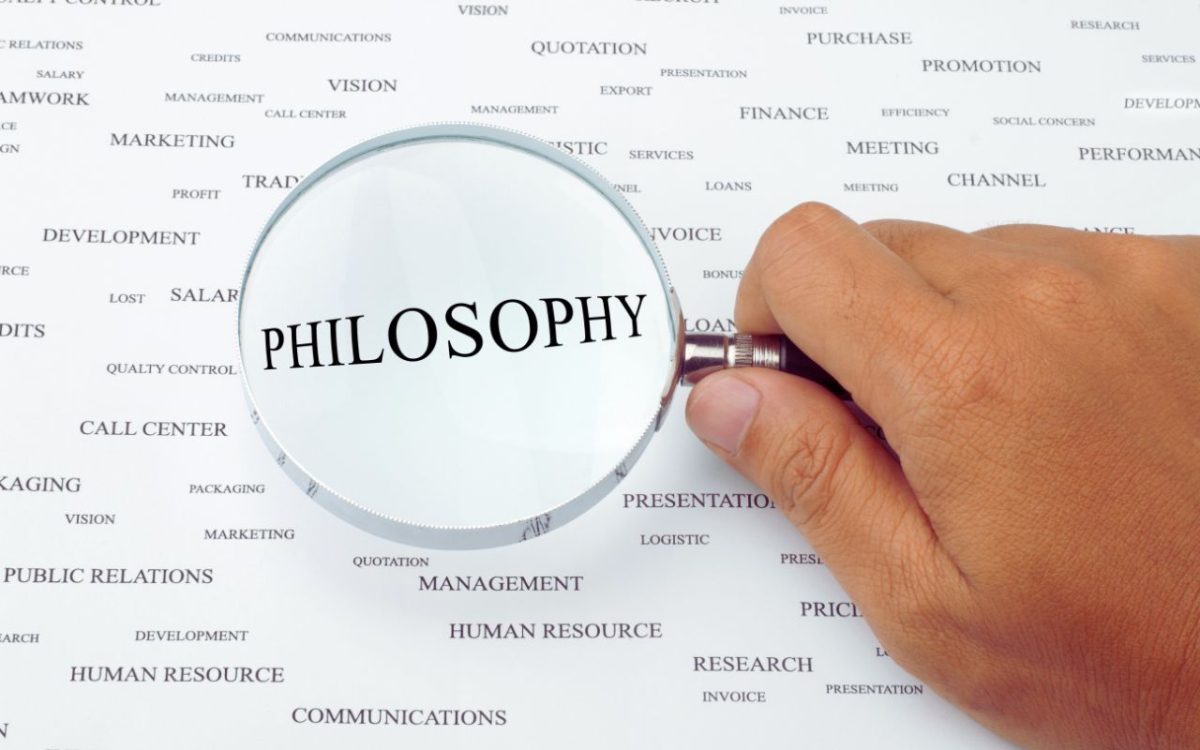
企業理念が現場に根づかない背景には、作り方や伝え方の問題があります。多くの企業では、経営者主導で理念を作成し、社員が「自分ごと」として実感できていない現状が見られます。
本記事では、理念が本当に現場に根づくために必要な採用・言語化・育成のアプローチなどについて解説します。
理念を「誰とどうやって」つくるかが浸透を左右する
理念の言葉は、誰がどのようなプロセスで作るかによって、その後の定着度が大きく変わります。社員を巻き込み、現場の実感を伴った理念づくりが、組織の一体感と実践力につながります。
ワークショップによる「自分ごと化」
たとえば、現場の社員やリーダー層も交えた理念づくりワークショップを定期的に行うと、日常の経験や本音を反映した言葉が生まれやすくなります。自分たちの体験から出てきたフレーズは、「他人事」ではなく「自分たちの仕事そのもの」として受け止められます。
その結果、理念は日々の判断や対話の場面で活用されやすくなります。
「言葉のきれいさ」より「共感できる具体性」
多くの企業で理念が浸透しない理由の一つが、表現が抽象的すぎたり長すぎたりして、現場で使いづらいことです。
たとえば「社会貢献」や「感謝の心」といった抽象語だけでなく、「現場でお客様にどう接するか」「どんな判断をしたときに理念が生きるか」など、具体的な行動例やエピソードと紐づけることが浸透のコツです。
経営者主導の限界と現場の巻き込み
経営者や役員だけで決めた理念は、現場の言葉と温度差が出やすく、掲げているだけで誰も語らなくなることが多いです。現場の体験や苦労を持ち寄り「自分たちの理念」を一緒に練り上げるプロセスが、その後の共感や実践に直結します。
実際、現場主導で理念を言語化した企業では、朝礼や会議で理念の言葉が日常的に使われるようになったという声も多く聞かれます。
理念浸透の出発点は「採用」にある

どんなに良い理念でも、共感や実践につながる仲間がいなければ根づきません。採用の現場こそが、理念文化のスタートラインです。
採用で「どんな言葉で伝えるか」がカギ
採用ページや求人票、面接などで、経営層だけが理念を語るのではなく、実際の現場社員や若手メンバーの言葉を積極的に盛り込むと、求職者は「この会社は本当に理念を大切にしている」と感じやすくなります。
どんなストーリーや具体的なエピソードで理念を伝えるかが、その後の文化づくりに直結します。
共感で入社した人が文化を広げる
理念に共感して入社した人は、自発的に理念を現場で体現しやすい傾向があります。
たとえば、入社後に理念に沿ったエピソードや体験を自ら発信したり、後輩に理念の意義を語る場面が増えることで、社内に新たな共感の輪が広がっていきます。
現場のロールモデルが増えると、理念文化がさらに根づきやすくなります。
採用時の「伝え方」と「誰が語るか」
実際の現場で働く社員が自分の言葉で理念を語ることで、求職者は「入社後のイメージ」が具体的に湧きます。
経営者や人事だけでなく、現場の社員が登場する面接やインターンシップ、社内イベントなどでの発信が、理念のリアルさや本気度を伝えます。
入社後の共感のプロセスを見守る重要性
理念に最初から共感していなかった人が、現場体験や仲間との関わりを通じて後から理念に共鳴することも多くあります。こうした変化のプロセスを丁寧に見守る姿勢が、組織の柔軟さと強さを育てます。
理念体現の現場体験が“共感”を生む
入社後に「理念は口先だけでなく、現場の判断や行動に根付いている」と感じることで、もともと理念に関心が薄かった社員も共感を深めていきます。
たとえば、「現場リーダーが理念に沿って意思決定している」「トラブル時に理念を基準に判断している」など、日常業務の中で理念が使われている姿を目にすることが、後からの共感や納得感につながります。
共感の種を育てる仕掛け
採用の場で「理念に100%共感できる人」だけを選ぶのではなく、入社後に理念の意義を体験しやすい仕掛けや、社員同士が理念について話し合える環境を用意しておくことが大切です。
たとえば、定期的な座談会や現場リーダーとの対話機会、理念に沿った表彰制度など、共感の種が育つ場を意識的に増やしましょう。
一緒に育てていく「理念」の文化
理念は押し付けたり一方的に教えるものではありません。日々の対話や経験、現場での成功・失敗を通じて、組織全体で共感の輪を広げていくものです。
経営者も社員も一緒になって、理念を言葉として、行動として、少しずつ「育てていく」ことが、長く愛される文化につながります。
理念は共につくり育てるもの
理念は経営者だけが作るものでも、壁に貼るだけのスローガンでもありません。社員と共に言葉を磨き、採用や現場体験を通じて「自分たちの文化」にしていくことが大切です。
押し付けではなく、日々の行動と対話から生まれる“共感の循環”が、理念浸透と組織の成長を支えます。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



