
インナーブランディングの実践ツールとして社内報を活用する企業は多いですが
「本当に社員に見られているのか」
「効果が出ているのか」
は多くの現場で悩みの種です。
ただ情報を配信するだけでは社内報の役割を果たせません。本記事では、社内報の「見る・見ない問題」の本質と、現場での工夫や仕組みづくり、会社ごとの合う・合わないの見極め方について詳しく解説します。
社内報が「見られない」本当の理由
多くの会社で社内報は形だけになりがちですが、その背景には「内容への関心の薄さ」「伝え方の単調さ」「現場との接点の少なさ」があります。
以下では、なぜ見てもらえないのか、その原因を具体的に掘り下げます。
ただ配るだけでは意味がない
社内報を社内サイトにアップしたり、メール配信しただけで「みんな見てくれるはず」と思わないでください。特に現場が忙しい会社では、受動的な発信だと情報が流されてしまい、内容を把握しないまま終わります。
配布だけで終わらず、「何を伝えたいのか」「どのタイミングで伝えるのが効果的か」まで計画する必要があります。
見せる努力・巻き込む工夫
「どうしたら見てもらえるか」を真剣に考え、実践することが社内報の成果を左右します。例えば朝礼の場で「今月の社内報はこの人のインタビューです」と紹介し、本人から一言コメントをもらうと興味が高まります。
また、内容も単なる連絡や業務報告でなく、現場のリアルな課題や成功体験、社員の本音エピソードを織り交ぜることで、自然に会話や議論が生まれやすくなります。
内容の質と話題性が「見たくなる」を生む
実際にむすびがサポートした大庄の座談会記事では、社員同士の本音のやりとりや具体的な事例紹介が「自分も読んでみたい」「この話題を朝礼で話そう」と現場の参加意欲を高めました。
情報の質やタイミング、声かけや巻き込み方をセットで工夫することで、読まれる社内報に変わります。
社内報は合う会社と合わない会社がある
どの会社でも社内報が有効とは限りません。自社の文化や社員の雰囲気、現場の温度感に合った発信手段を選ぶことが重要です。
社内文化とツールのフィット感
社員同士の交流や情報共有が盛んな会社では、社内報が話題になりやすい傾向があります。一方で、もともと会話が少ない現場や、一方通行の情報伝達が主流の会社では、社内報が定着しにくい場合もあります。
実際に、配信しても誰も話題にしない、読まれない状況が続くなら、やり方自体を見直すことが必要です。
試行錯誤と撤退の判断
社内報は万能ツールではありません。内容や伝え方を変え、見てもらう努力を重ねた上で、それでも定着しない場合は、他の手段に切り替える勇気も大切です。
現場のニーズや文化を観察し、うまくいく方法を柔軟に模索する姿勢が、結局は一番の近道となります。
方法論だけに頼らず、現場に合わせる視点
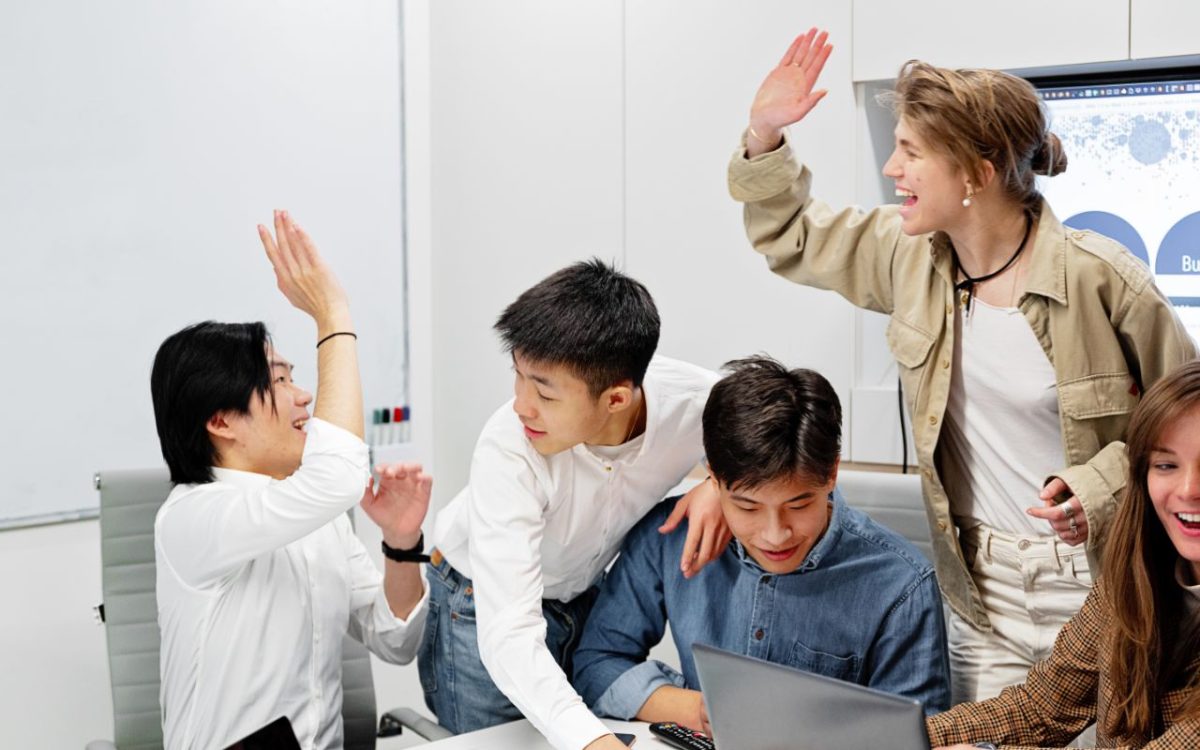
「どのやり方が正解か」だけに目を向けると、自社で失敗しやすくなります。現場や社員のタイプ、部署の特性など細かい違いを見極めて、柔軟にコミュニケーション設計をすることが大切です。
採用現場にも共通する目利きの重要性
採用活動でも「この候補者はどの部署と合うか」「社長が会うべきか現場社員が会うべきか」など、相性や現場目線で判断するケースが増えています。
社内報も同じで、一律のやり方ではなく、現場ごとにフィットする方法を模索する必要があります。
方法よりも現場に合わせる姿勢が効果を左右するのです。
不変の法則は現場に宿る
採用・インナーブランディングとも、方法論を真似るだけでは成果は続きません。社内の多様性や温度差を認め、現場と対話を重ねながら、会社ごとの「不変の法則」を見つけていくことが、長期的な浸透や組織強化のポイントになります。
社内報は「伝え方・現場目線・文化適応」がカギ
社内報はただ発信するだけではなく、内容の工夫・現場の巻き込み・自社文化への適応が不可欠です。見てもらう努力を継続しながら、合わない場合は新しい手法を模索し、現場のリアルな声と向き合う姿勢がインナーブランディングの効果を高めます。
社内報については、以下の記事も参考にしてください。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



