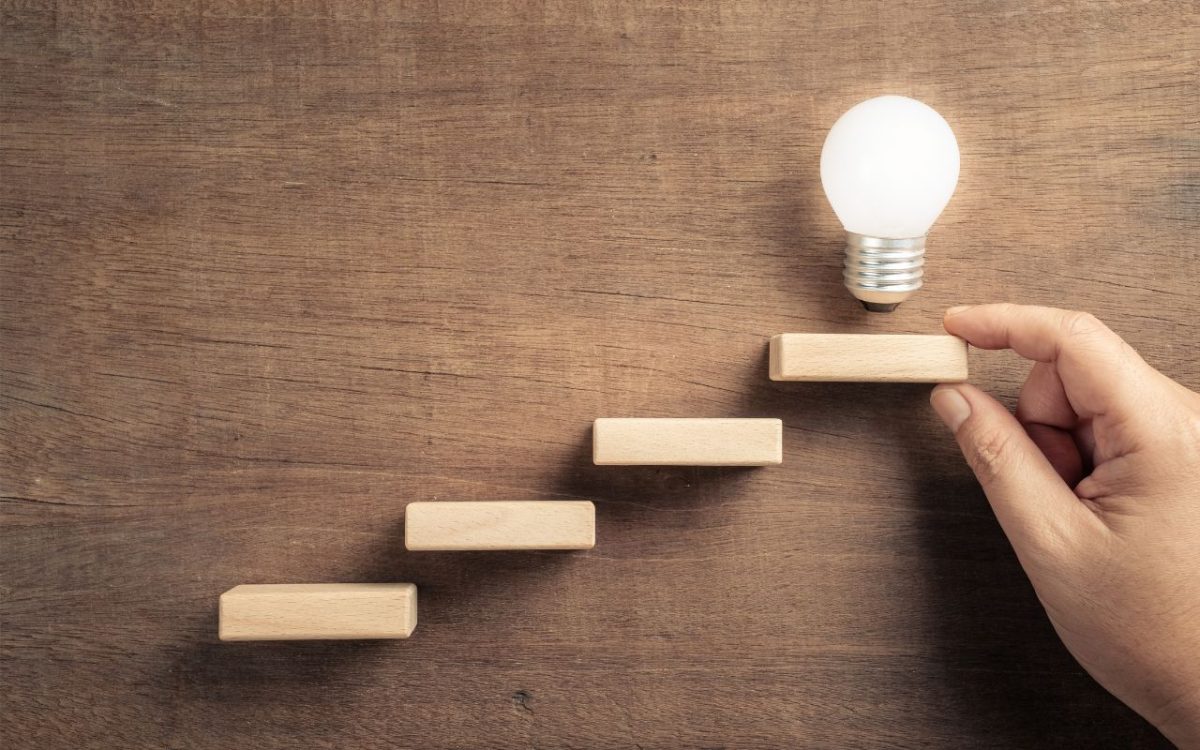
企業やブランドが新規顧客や従業員を単なる利用者として扱う時代は過ぎ、継続的な支持者=ファンの存在が経営に不可欠となっています。ファンはリピート購入や自発的な情報発信、採用力の向上など、さまざまな面で企業活動を支えています。
本記事では、ファンを増やすために必要なプロセスや現場で活用できる具体策について、段階ごとに整理します。
ファン化の基本ステップ
ファン化には「認知・興味」「共感・信頼」「体験」「継続的な関係性」の4つの段階があり、それぞれの段階で適切な施策が必要となります。以下では各ステップの具体的な意味や役割、実際の企業で行われている工夫や現場の事例をもとに、成功のポイントを整理します。
認知・興味を持ってもらう
新しい顧客や従業員候補に自社の存在や魅力を知ってもらうためには、発信の方法やタイミングを工夫する必要があります。
たとえば、特徴を明確に伝えるホームページや動画を用意したり、SNSを活用して日常的な情報を提供することで興味を持つきっかけが増えます。自社らしさが伝わる接点を増やすことで、認知から興味への流れを作ります。
共感・信頼を高める
企業やブランドへの共感や信頼は、情報の透明性や一貫した姿勢の発信から生まれます。現場社員や経営者の声を自社メディアやSNSで公開したり、製品やサービスの選定理由や改善プロセスを伝えることで、相手の理解と納得を促せます。
正直な情報提供と姿勢の一貫性が、共感と信頼の獲得に直結します。
体験を通じて満足度を上げる
実際にサービスや商品を体験することで、顧客や従業員の納得感や満足度が大きく向上します。
たとえば飲食店の試食会やオンラインストアの無料サンプル送付、職場見学やインターンなどが挙げられます。リアルな体験の提供が「もう一度使いたい」「働きたい」と思うきっかけになります。
継続的な関係づくりとコミュニケーション
一度の接点だけではファンは定着しません。継続的な関係を築くには、定期的なフォローやコミュニケーションが重要です。
たとえばリピーター向けの限定イベントやニュースレター、購入者へのアフターフォローや感謝状の送付など、接点を維持し続ける工夫が求められます。継続的なやりとりが長期的なファン化に欠かせません。
各ステップで重要な取り組み
ファン化ステップは理論だけでは機能せず、現場での具体的な施策と仕組みづくりが不可欠です。以下では、ブランドメッセージや現場体験、顧客や従業員の声を活かす工夫など、各段階で実践的に役立つ取り組みをわかりやすく紹介します。
情報発信とブランドメッセージの統一
情報発信の内容やタイミングを統一することで、顧客や従業員が混乱せずにブランドを理解できます。複数のチャネル(Webサイト、SNS、パンフレット)でメッセージやビジュアルを一貫させる工夫が有効です。たとえば、アパレル企業が広告・店舗・ECサイトで一貫したブランドストーリーを展開し、消費者に強い印象を残した例があります。一貫性は信頼につながり、ファン化の基盤となります。
現場体験やイベントの設計
現場での体験やイベントは、商品やサービスのリアルな魅力を伝える有力な手段です。工場見学、現場ツアー、実際の作業体験、リモートワーク説明会など、参加型の仕組みが効果的です。
現場のリアルな体験が、理解とファン化を深めます。
顧客・従業員の声を活用した改善
顧客や従業員の本音を集め、サービスや職場環境の改善に反映する取り組みが、ファン化の後押しになります。実際の声を迅速に取り入れる姿勢が、長期的なファン層の拡大に役立ちます。
ファン化ステップを継続するために
ファン化は短期間で完成するものではなく、日常的な情報発信・現場体験・継続的な対話・改善の積み重ねが必要です。各ステップの取り組みを定期的に見直し、時代や市場の変化にも柔軟に対応することが大切です。
顧客や従業員と双方向で関係を深める工夫を続けることで、強いファン層を維持できます。単なる施策の繰り返しではなく、現場や利用者の声を大切にしながら、企業やブランドのファン化を着実に継続してください。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



