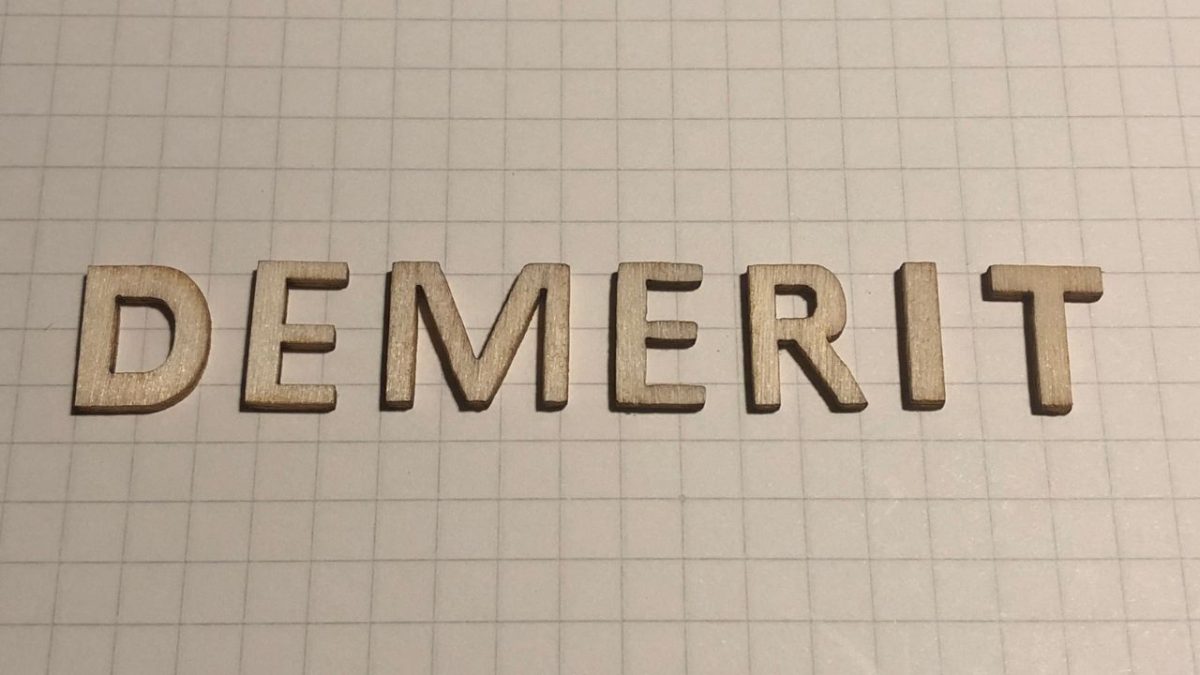
インナーブランディングを進めることで組織が強くなると聞いても、経営者や現場担当者の多くは「本当にうちでできるのか」「大変そうだ」と不安を感じることがあります。実際、制度やカルチャーを根本から見直す取り組みには、避けて通れないデメリットも存在します。
本記事では、よくある課題や懸念点を整理し、デメリットを理解したうえで、それでもインナーブランディングを推進する意味と現実的な対処法を考えていきます。
インナーブランディングで感じやすいデメリット
インナーブランディングは現場で新たなコミュニケーションや制度づくりが求められるため、導入時には負担や混乱を感じることもあります。
規模や組織風土によっては、日常業務と両立する難しさや、一部社員の反発など、運用上の課題が表面化する場合も少なくありません。
面倒臭さ・時間的コスト
インナーブランディングを進める過程では、「制度設計をどうするか」「社内に考え方を浸透させるミーティングや研修をどう組み込むか」など、日常業務とは別に新たなタスクやコミュニケーションの手間が発生します。特にトップダウン型の経営スタイルや、現場に権限委譲がされていない会社の場合、「なんでこんなに手間がかかるのか」「もっと効率的にできないのか」と感じることも多いでしょう。
人数が少ない会社ではまだ対応できますが、規模が大きくなるほど調整や合意形成にも時間がかかります。
退職リスク・社内ハレーション
インナーブランディングを本格的に始めると、「会社の理念や価値観」に強く共感しない社員が違和感を抱き、「今のままの会社じゃ嫌だ」「やり方が合わない」と感じて退職するケースも出てきます。とくに現場の制度や評価基準が変わるタイミングや、会社の方向性がはっきりと示された時などは、短期的に離職が増えるリスクがあります。
このハレーションは避けられませんが、経営側が最初に「今後はこういう考え方でやる」「合わない人は無理に引き留めない」というスタンスを明確にしておくことが重要です。
一時的な負担増と業務量の調整
既に一人当たりの仕事量が多く「これ以上抜けられたら困る」という会社では、インナーブランディングの推進に二の足を踏むこともあります。人員不足の中でさらに業務が増えるのでは、現場にしわ寄せがいくためです。
ただ、ここで一時的な大変さを乗り越えてでも自分たちの会社を良くしたいという覚悟が経営層にあるかどうかが、取り組みの成否を分けます。社長自身が「短期的に負担が増えるけど、長い目で見れば必ず良くなる」と現場に伝え、理解を得ておくことが不可欠です。
インナーブランディングを実践すべき理由

インナーブランディングには確かに手間やリスクがありますが、それ以上に長期的な成長や組織力向上のメリットが大きいのが事実です。
企業の方向性をはっきりさせ、社内のコミュニケーションやチーム力を高めるためにも、この取り組みを避けて通ることはできません。
成長志向の会社にはインナー施策が効率的
「会社をもっと成長させたい」「今より一段上の組織を目指したい」という社長や経営チームにとっては、インナーブランディングが最も効率的な投資のひとつです。外部コンサルに丸投げして戦略だけ作るのではなく、内部で現場と一体となって進めることで、人材育成と会社の基盤強化が同時に進みます。
人数が少ない会社ほど変化は早く、30人規模と1万人規模では速度感が大きく違いますが、小さいうちから着手することで成長期の課題を早めにクリアできます。
制度設計や専門領域は必要に応じて外部活用
インナーブランディングをやる中で、必要に応じて「制度設計」「評価基準の整備」などは外部の専門家に部分的に依頼するのも選択肢です。全部を自社だけで抱え込むのではなく、足りないノウハウやリソースは適宜補完しながら、自分たちで進める部分を明確にしておくと、負担を分散しやすくなります。
社長の覚悟と会社を変える理由の共有がカギ
インナーブランディングは、面倒さや一時的な混乱・離職リスクを避けられません。しかし、そのプロセスを経て理念や価値観が浸透した組織は、長期的な成長や人材の質の向上、企業の競争力強化につながります。
社長自身が目的や理由を社員や幹部に説明し、全社でなぜやるのかを共通認識にしておくことが、現場への納得感を高める最大のポイントです。一時的な負荷を乗り越えた先に、自分たちの会社がより良くなるという成果を目指しましょう。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



