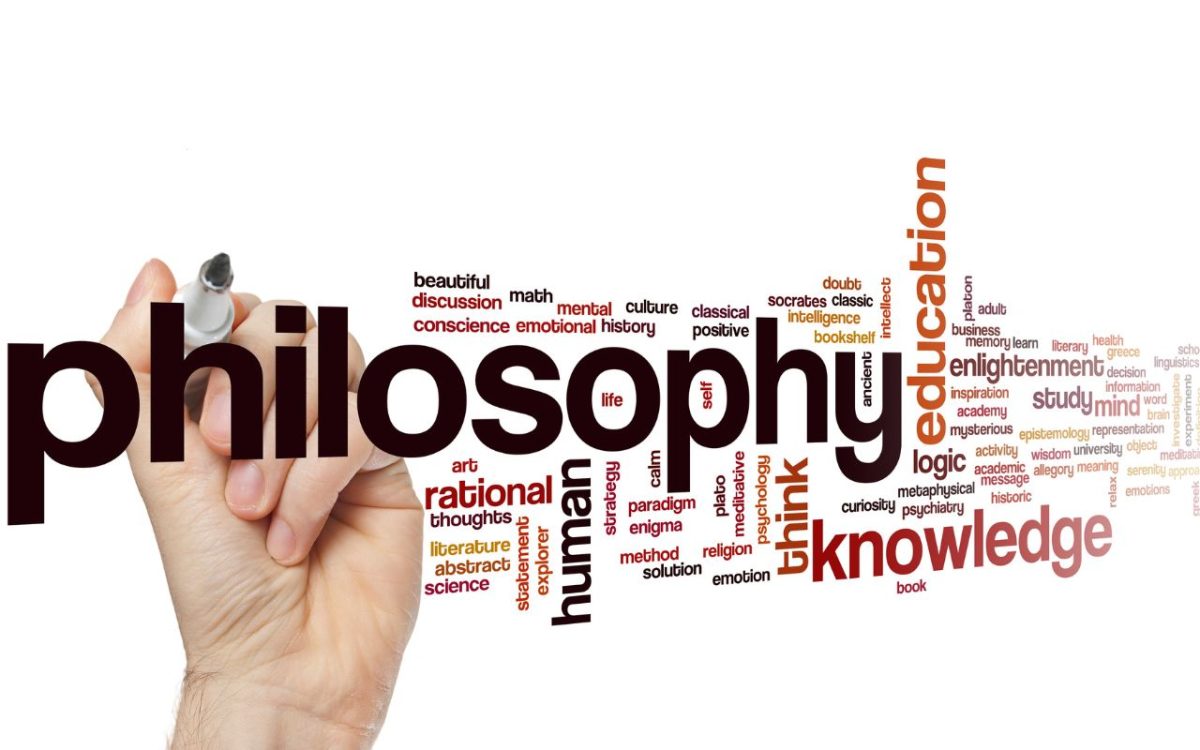
多くの企業が「理念」を掲げていますが、「実際に社員の行動や判断に活きている」と感じている経営者は多くありません。
「うちの理念は社員に伝わっていない」「掲げてはいるけれど、現場では使われていない」という悩みは、どの組織でもよく耳にします。
理念の言語化まではできても、その先で壁にぶつかっている会社がほとんどです。この壁を超えなければ、組織は一体感や本当の強さを持つことができません。
本記事では、「なぜ理念が伝わらないのか」「本当の意味で理念を浸透させるには何が必要か」を現場の視点から解説します。
理念が「伝わらない会社」が抱える根本的な問題
企業理念を掲げているものの、「社員に浸透していない」と悩む経営者は少なくありません。理念を言語化し社内に掲示しても、現場での行動や判断が理念と無関係なままになっている会社は多いです。
こうした状態が続くと、組織に一体感が生まれず、期待した成長も実現しません。経営層がいくら「理念が大事」と強調しても、社員にとっては遠い存在のままです。
「理念を共通言語にできていない」ことが最大の壁
多くの企業では、理念を「共有」する活動は行われていますが、それが「浸透」にまでは至っていません。理念が本当に根付いている会社では、現場の社員が迷った時や新しいチャレンジをする際に、理念を自然に判断基準として使っています。
しかし、形だけの共有や掲示にとどまっている場合、社員は理念を自分の言葉として語ることができません。理念を共通言語にするには、社員一人ひとりが「自分の判断や行動に理念をどう活かせるか」を理解し、現場のあらゆる意思決定で理念が具体的に機能している状態をつくることが重要です。
「共有」と「浸透」はまったく違う
理念を「伝えた」「知っている」だけでは組織は動きません。現場で実際に使われていることが大事です。この差を理解しないまま、掲示や朝礼だけで満足してしまうと、理念は形骸化し、社員の共感も失われます。では、何が両者の違いを生み出すのでしょうか。
理念が使われてこそ浸透になる
本当に理念が浸透した会社では、顧客対応で迷った時や、新人教育、会議など、日々のあらゆる場面で「理念を基準に考える」という姿勢が見られます。例えば、「この判断はうちの理念に合っているか?」と自問したり、先輩が新人に「うちの理念でいうとこうだよ」と説明したりする光景が自然に生まれます。
共有と浸透の違いは、理念が日々の現場で判断や行動の言語として具体的に使われているかどうかにあります。知っているだけの理念は、現場で役立たず、やがて忘れられていくリスクがあります
なぜ理念は現場で使われないのか

経営者がどれだけ強く理念を語っても、現場の温度感や日常のリアリティに合わなければ、社員の行動は変わりません。理念が現場の言葉に翻訳されていないことが、最大の障害になっています。
ここを乗り越えなければ、どれだけ立派な理念でも形だけで終わってしまいます。
理念が「使えない」のは翻訳不足が原因
経営層の言葉や理想を、現場の社員が自分の業務や判断に落とし込めていない場合、理念は使えない言葉になりがちです。たとえば、「挑戦」という理念があっても、現場では「何をどこまでやっていいのか」「失敗しても評価されるのか」が曖昧なままだと、誰も理念に沿ったチャレンジができません。
理念は現場の状況や悩み、社員のリアルな声をくみ取って、現場で実際に役立つ言葉に翻訳する作業が必要です。この翻訳作業がなければ、どれだけ理念を強調しても意味がありません。
理念は「掲げる」ものから「育てる」ものへ
理念は一度作ったら終わり、というものではありません。組織の成長や現場の変化に合わせて、常にアップデートし続けるべきものです。
経営層の想いや価値観を「現場で使える形」に落とし込み、社員の声や現実に応じて翻訳・進化させることが、理念を生きたものに変えるコツです。
理念の現場翻訳とアップデート
実際の組織づくりでは、「理念はこうあるべき」というトップの発信を鵜呑みにするのではなく、社員と対話を重ねながら「現場でどう使われるべきか」を具体的に話し合うことが必要です。
理念を定期的に見直し、現場の声や課題を踏まえて表現や運用を柔軟にアップデートしていくことで、社員が納得しやすい「使える理念」へと変わります。
理念の育成は一度きりのイベントではなく、組織の成長プロセスそのものです。
採用活動こそ理念浸透の最前線
採用の現場でも、理念が単なるスローガンにとどまってしまいがちです。しかし、実際には面接や説明会、入社後の教育まで含めて、理念を「現場で伝わる行動言語」に翻訳することが不可欠です。
入社後に「聞いていたことと違う」とミスマッチを生むのは、この翻訳が足りていない証拠です。
採用ブランディングは理念翻訳の装置
採用ブランディングの本質は、理念を「現場で通じる言葉」に落とし込み、求職者が自分ごととして理解・共感できるように設計することです。
たとえば、面接や会社説明会で理念に基づく具体的なエピソードを共有し、選考や評価基準、内定後のフォローまで一貫して理念が使われていることを実感してもらうことが重要です。現場の社員が同じ温度で理念を語れる状態をつくることで、入社後の定着や早期離職防止にも直結します。
理念浸透のための具体的ステップ
理念を現場で本当に使えるものにするためには、「核を抽出する」「現場や採用現場に翻訳する」「体験と一貫性を設計する」という実践的な段階を踏む必要があります。抽象論だけでなく、行動につなげる仕組みを作ることが大切です。
理念の核を現場目線で抽出・翻訳・一貫させる
まず、経営者が本当に大事にしたい価値観や判断基準を、抽象論にせず現場の具体例で表現します。次に、その言葉や基準を現場の状況や職種ごとにカスタマイズし、全員が同じ言葉で語れる状態を作ります。そして、面接・説明会・内定フォロー・教育まで一貫して理念を体験できるように設計することで、理念は単なる言葉から組織の血肉に変わります。
理念の浸透は経営の最重要課題
理念が現場で行動や対話の「共通言語」として使われることで、組織の一体感と持続的成長が生まれます。浸透のカギは「現場への翻訳」と「日常的なアップデート」。
採用や育成、現場の小さな対話の中で理念が使われる組織こそが、理念を生かす会社として強くなります。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



