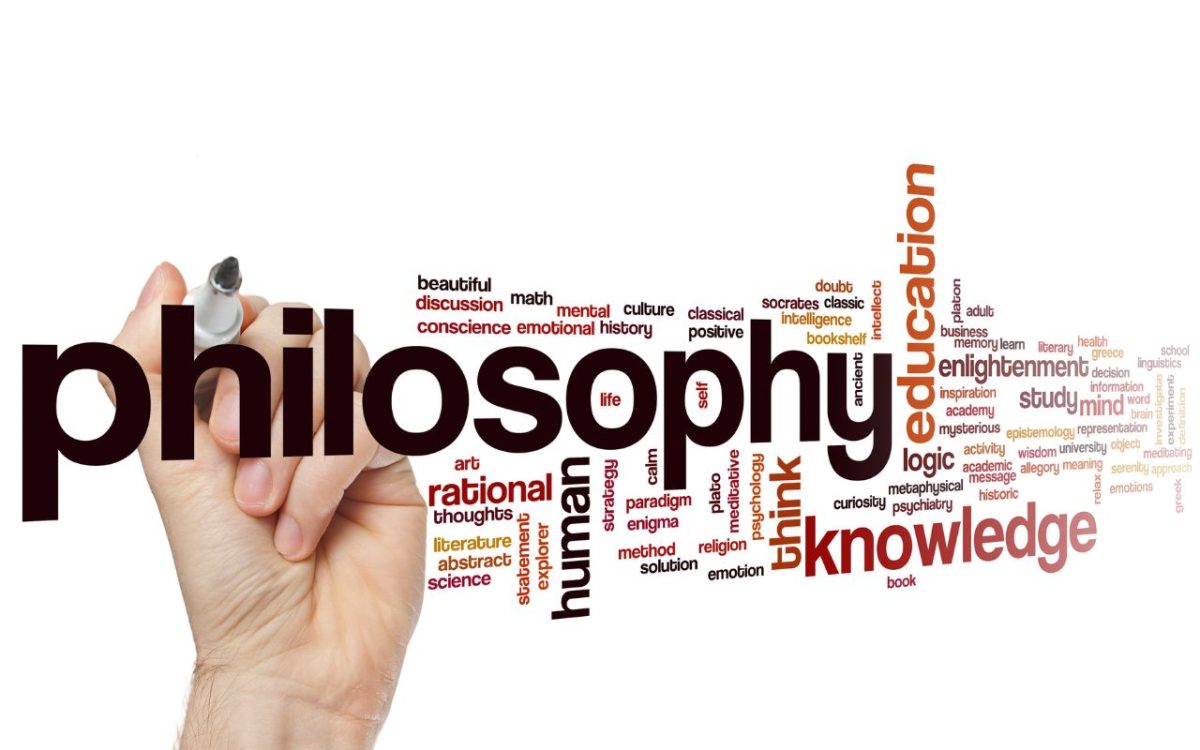
企業理念をどれだけ明文化し、ポスターや冊子にまとめたとしても、実際に社員の行動に落とし込まれなければ意味を持ちません。理念の“形骸化”を避け、社員一人ひとりが自分ごととして捉えるには、どのような打ち手が必要なのでしょうか。
本記事では、理念浸透のために不可欠とされる「制度・仕組み・仕掛け」の役割と、その運用における“意図の伝え方”の重要性について解説します。
理念は「制度」や「仕掛け」がなければ浸透しないのか?
理念を体現してもらうためには、制度や評価への反映が不可欠だという議論があります。しかし、それが唯一の手段というわけではありません。
会社の規模やフェーズによって最適解は異なる
企業の規模や組織の成熟度によって、理念の浸透方法は多様です。
例えば、数千人規模の企業であれば、冊子やポスターを使って全社的なメッセージ発信を行うことも一定の効果を持ちます。しかし多くの場合、それだけでは終わってしまうのが実情です。
理念を組織に根づかせるためには、「制度」「仕組み」「仕掛け」だけではなく、それらをどう“運用”するか、つまり「伝え方」や「想いの込め方」が問われます。
「制度」「仕組み」「仕掛け」の三位一体が浸透の土台になる
理念が日常業務とつながらず、社員にとって“他人事”のように映ってしまう原因のひとつが、実行手段の分断です。評価制度だけを整えても、行動が促されるとは限りません。
制度:評価や報酬を通じた理念の可視化
- 理念に沿った行動に対する評価項目の設置
- インセンティブや賞与制度への反映
- 昇進・任用時の価値観マッチの確認
仕組み:理念実践を支える日常的なフロー
- 朝礼や日報における価値観共有の時間
- MVP表彰などの称賛文化の整備
- フィードバックループの構築
仕掛け:自発性と参加意欲を促す演出
- 理念に基づいた社内イベントや合宿
- ワークショップや対話会の設計
- 社内報・動画・ポスターなど視覚的訴求
このように、制度・仕組み・仕掛けを単体で行うのではなく、相互に連動させて運用することで初めて理念が実体化されていきます。
人は「怠惰」である前提に立つ
理念が自然と浸透していく組織は稀であり、通常は多くの仕掛けと工夫を重ねる必要があります。これは、人間の性質を正しく理解するところから始まります。
「人は基本的に怠惰」という前提がマネジメントの出発点
人は放っておけば“考えなくても良い状態”を選びがちです。これは悪ではなく、人間の本能に近いものです。だからこそ、経営者や管理職は「そうじゃない在り方」を示す必要があります。
- 毎朝の一言コメントで理念の要素を伝える
- 表彰制度でのコメントに理念文言を必ず含める
- イベント開催時には“なぜやるのか”を必ず明示する
このような「繰り返し」が、社員の中で理念を“考える習慣”として根づかせていく第一歩になります。
制度や仕組みは「メッセージ」である
制度や仕掛けは、それ自体が経営からの無言のメッセージでもあります。「理念を体現してほしい」という意志を、制度設計の形で伝えているとも言えるのです。
なぜそれをやるのか?を伝え続ける
多くの企業では制度やイベントを導入する際、「やります!」というアナウンスだけで終わってしまいます。しかし、それだけでは行動は変わりません。
大切なのは、「なぜこれをやるのか?」を丁寧に伝えることです。
- 朝の会をやる理由:理念の再確認と共有
- MVP表彰をやる理由:価値観の体現を称賛する文化づくり
- 初期払い制度の導入:安心して理念実践に取り組んでもらうための支援
こうした“背景の共有”がなければ、制度はただの「管理手段」になってしまい、社員の心には響きません。
飲み会やイベントも理念と結びつける
例えば、忘年会や社員旅行など、日常的な社内イベントにおいても、理念を伝える機会として設計することが可能です。
“ただの催し物”にしないために必要な視点
多くの企業は「イベントをやること」自体が目的化してしまいがちです。しかし、目的は社員のつながり強化や価値観の共有であるはずです。
- 忘年会での乾杯挨拶に理念との接続を盛り込む
- ワークショップに企業のミッションをテーマとして設定
- 社員の発表テーマに「理念との関係性」を組み込む
こうした設計を通じて、イベントは“理念を体験する場”に変わります。
経営者は「飽きても伝え続けること」が仕事
理念を何度も伝える中で、発信側(特に経営者やリーダー)は「もう何度も言った」と感じるようになります。しかし、受け手側が“ようやく腑に落ちる”のは、発信側が100回目を迎えた頃かもしれません。
伝える本人が飽きていても、伝えることはやめない
理念浸透において重要なのは、“頻度”ではなく“執念”です。
- 飽きても語り続けること
- 自分が何度言ったかではなく、相手がどう受け取ったかを重視すること
- 言葉を変え、媒体を変え、伝え続けること
これが理念浸透の本質であり、組織文化の土壌を耕すための経営の役割です。
制度は「理念の翻訳装置」。繰り返しと意図が浸透を生む
理念を浸透させるには、「制度・仕組み・仕掛け」を整えることは手段にすぎません。そこにどんな意図を持たせ、どう伝えるか、どれだけ繰り返すかが、理念が“形”になるかどうかを左右します。
制度は理念の翻訳装置であり、仕掛けはその翻訳を行動に変えるためのスイッチです。伝わらないのではなく、伝わる設計と、伝える覚悟が足りないだけかもしれません。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



