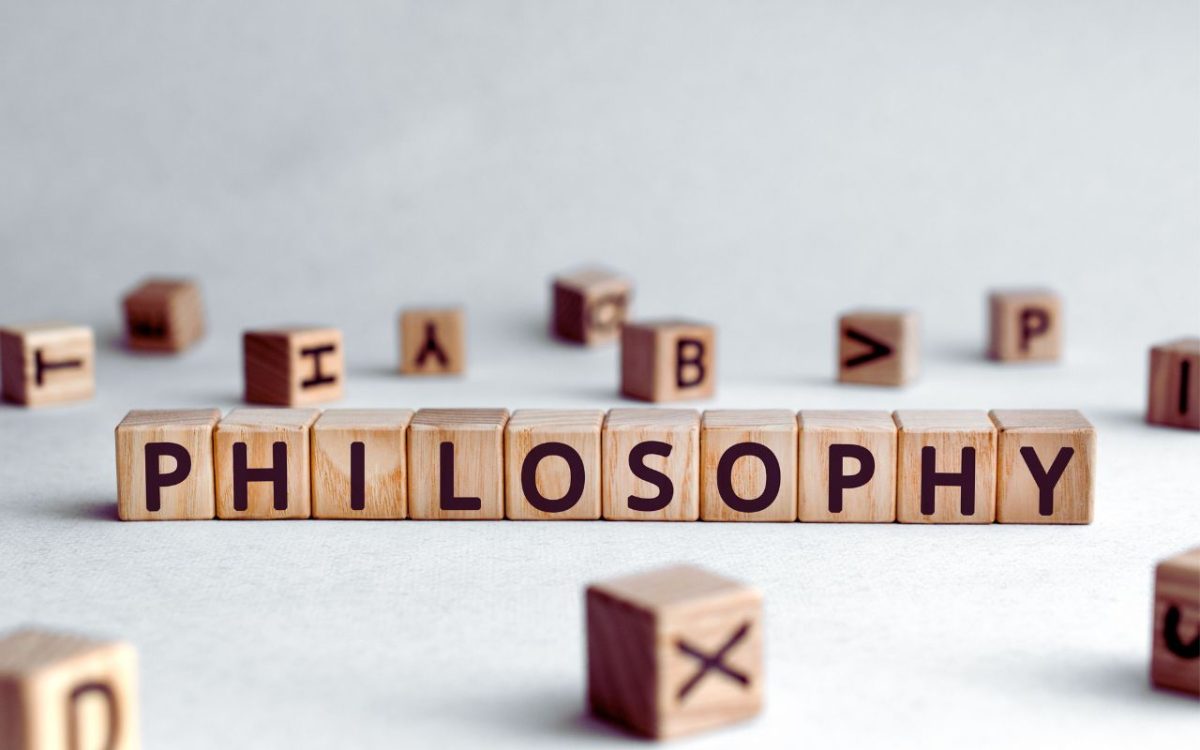
企業理念は、単なるスローガンや社内ポスターに掲げる言葉ではありません。経営者の価値観や組織の存在意義が凝縮された「企業の核」であり、事業成長や人材定着の土台ともなる重要な要素です。
しかし多くの現場では、「理念はあるが浸透していない」「言葉はあるが活用されていない」といった課題が繰り返されています。
本記事では、「理念はつくるものではなく、気づくもの」という視点から、企業理念の本質的な意味や、その発掘・浸透のプロセスについて解説します。また、採用や育成の場面において理念がどのような役割を果たすのか、経営戦略との関係性も踏まえて紐解きます。
理念は「つくる」ものではない、「気づく」ものである
企業理念は、ゼロから創作するものではありません。経営者がこれまでの人生で培ってきた価値観や判断基準、事業選択の積み重ねの中に、すでに存在しているものです。理念とは、企業の根底に流れる「魂の輪郭」であり、ただ言語化されていないだけなのです。
理念の原型は経営者の意思決定に宿る
過去にどのような選択をしてきたのか、なぜその道を選んだのか。そこに理念の原型が見えてきます。多くの経営者は、自分の判断に一貫性があると気づいていませんが、それこそが理念の胎動です。
現場にも理念のヒントがある
理念は経営者の中だけにあるものではありません。現場の声や従業員の違和感、顧客との対話の中にも、企業が本来目指す価値のヒントが隠れています。
これを経営者と社員の対話によって発掘していくことが、理念づくりの本質です。
理念づくりは「発掘」かつ「共創」のプロセス
理念はコピーライターが生み出す言葉ではなく、組織内の対話を通じて見えてくる共通言語です。経営者の想いを起点に、社員の価値観とすり合わせながら言語化していく過程こそが、理念づくりであり、共創による意味の再発見です。
理念への共感が、社員の活躍と持続を生む
理念は、単なるスローガンではありません。社員が共感し、行動に移し、結果を生み出すための内的動機の源です。理念共感が、採用・定着・成果にまで影響するのは、精神論ではなく構造的な事実です
理念に共感する人材が自然と動き出す
入社時から理念に共感している人、あるいは入社後に理念と自己を重ね合わせていく人。いずれにせよ、自社の価値観と個人の物語が重なったときに、自発的な行動が生まれます。
これは採用後の活躍の条件でもあります。
共感は偶然ではなく設計されるもの
理念を採用活動や入社後の育成に一貫して組み込むことで、求職者の共鳴を設計できます。理念が採用コピーに現れ、面談で語られ、実際の職場で裏切られずに体現されることが、信頼と活躍を生む構造につながります。
データで証明された理念共感と活躍の相関
私たちが行ってきた複数のプロジェクトにおいて、「採用時の理念共感の有無」と「入社後の活躍」には明確な相関関係が見られました。これは感覚ではなく、再現性ある構造として存在する事実です。
理念は「伝える」だけではなく「浸透」させる必要がある

理念がうまく伝わらない、社員が理念に共感しない。こうした課題の多くは、「伝達」の不十分さではなく、「浸透」の欠如に原因があります。浸透とは、社員一人ひとりの行動に理念が現れる状態を指します。
浸透とは、日常の意思決定に理念が使われること
理念が本当に浸透している組織では、社員が日々の判断において理念を基準に考え、会話や教育の中でも理念を用いて説明します。
ただ掲げるのではなく、実際に“使える言葉”として根付いている必要があります。
浸透を阻むのは、翻訳の不足
トップの想いが現場に届かない背景には、「言葉の翻訳不足」があります。理念が社員の文脈や日常言語に変換されていない場合、それは使いにくい抽象的なスローガンになってしまい、浸透は起きません。
理念の浸透はインナーブランディングの本質
インナーブランディングとは、企業の内側に理念を宿し、現場で使える言葉に育てていくプロセスです。採用ブランディングもこの一部として、採用時の期待値と入社後の実態の一致を支える重要な役割を果たします。
理念は企業成長の核となる
理念は「つくる」のではなく「気づく」ものです。経営者の想いと現場の声をすくい上げ、共通言語として再発見し、組織全体で共有・浸透させていくことが求められます。
理念に共感した社員は、主体的に動き、長く働き、成果を出す。その構造を実現するためには、理念を軸に据えたインナーブランディングと採用ブランディングの設計が不可欠です。
経営における理念の重要性を再認識し、組織の中で育てていく取り組みが、持続的成長の礎となります
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



