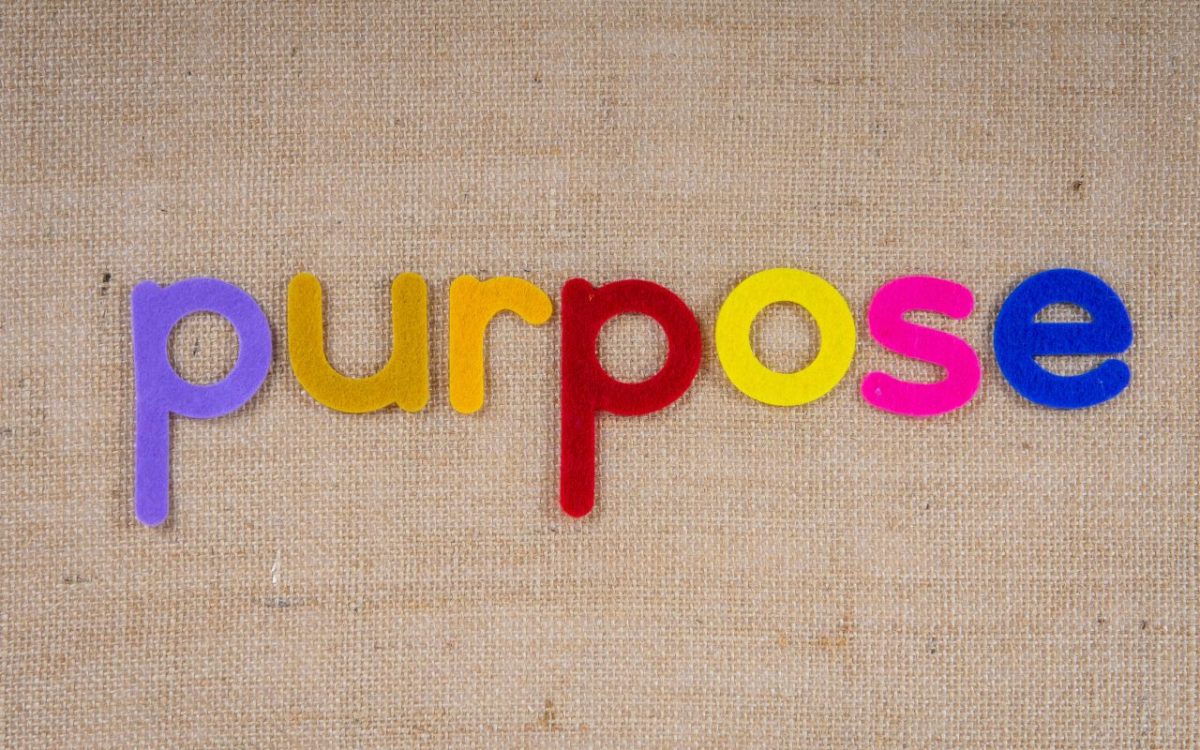
「パーパス経営」や「パーパスブランディング」といった言葉が、日本でも徐々に耳にされるようになりました。経営層だけでなく、ブランド戦略や人事領域においても「パーパス」が重要だと語られる場面が増えています。
しかし、「それは経営理念と何が違うのか?」「なぜ今、パーパスなのか?」といった疑問を感じる経営者も多いのではないでしょうか。本記事では、パーパスという概念の由来と、経営理念との違いを整理しながら、自社でどう向き合うべきかを考えていきます。
パーパスとは何か?どこから始まったのか?
パーパスという言葉は、単なる「目的」を超えて「存在意義」や「社会的使命」を表します。企業が事業活動を通じて、どのように社会に貢献するのかを明文化したものであり、近年ではグローバル企業を中心に導入が進んでいます。
以下では、その起源や背景をひもといていきます。
アメリカのCEOラウンドテーブルでの発信がきっかけ
「パーパス」という概念が広く注目されたきっかけは、2019年、米国ビジネス・ラウンドテーブル(CEOラウンドテーブル)と考えられます。「企業の目的は株主の利益最大化にとどまらず、従業員・顧客・地域社会といったステークホルダー全体に貢献すべきだ」と、資本主義的な企業観に対する大きな転換を図りました。
資本主義社会における“社会的責任”の必要性
アメリカでは長年、「企業は株主に利益をもたらす存在である」という原則が主流でした。ですが、格差の拡大や環境問題の深刻化、倫理的問題の表面化など、社会的課題が経営に影響を及ぼすようになり、経済成長と社会貢献のバランスが問われ始めたのです。
こうした背景から、「何のために存在する企業なのか」という問いが再浮上し、それに対する答えとして「パーパス(存在意義)」が定義されるようになりました。
理念との違いは「社会との関係性」にある
パーパスと経営理念は非常に似ています。どちらも企業の根本的な価値観や存在理由を表現するものですが、違いがあるとすれば、それは「視点」です。
経営理念はどちらかというと「社内の価値観の統一」に重きが置かれますが、パーパスは「社会に対してどういう価値を提供するか」に重点が置かれます。つまり、理念が「自分たちに向けた言葉」だとすれば、パーパスは「社会に向けたメッセージ」と言えるのです。
パーパスを導入することで起きる変化
パーパスを明確にすることで、社内外にさまざまなポジティブな変化をもたらすことができます。導入の効果は企業のフェーズによって異なるものの、共通して言えるのは「価値観の再定義」と「共感の醸成」によって組織が強くなるという点です。
社内の価値観の再整理につながる
パーパスを定義するプロセスは、社内の価値観や文化を見直す機会でもあります。社員一人ひとりが「うちの会社は何のために存在しているのか」を考え、共有することで、理念やミッションがただの言葉ではなく、行動指針として根づいていきます。
特に、世代交代や事業の転換期においては、パーパスによって組織の再定義が可能になります。
顧客や社会に向けたメッセージになる
現代の消費者は、商品そのものよりも「企業の姿勢」や「社会的な意義」に共感して商品を選ぶ傾向があります。パーパスが明確であれば、それは広告コピー以上に強い説得力を持ち、ブランドそのものの評価に直結します。
企業が「何をやっているか」よりも「なぜそれをやっているか」を伝えることで、深い共感や信頼を獲得することができるのです。
経営理念と重なる部分がある場合の対応方法
多くの企業はすでに「経営理念」を持っているため、「今さらパーパスを追加する必要があるのか?」と疑問を抱くかもしれません。しかし、既存の理念と重なる内容であっても、対外的にメッセージを出すときの「見せ方」として再整理することには意味があります。
経営理念をあえて変えるのではなく、文脈に応じて「パーパス」として表現することで、時代に合った伝え方が可能になります。
「パーパスを定義する」前に考えるべきこと
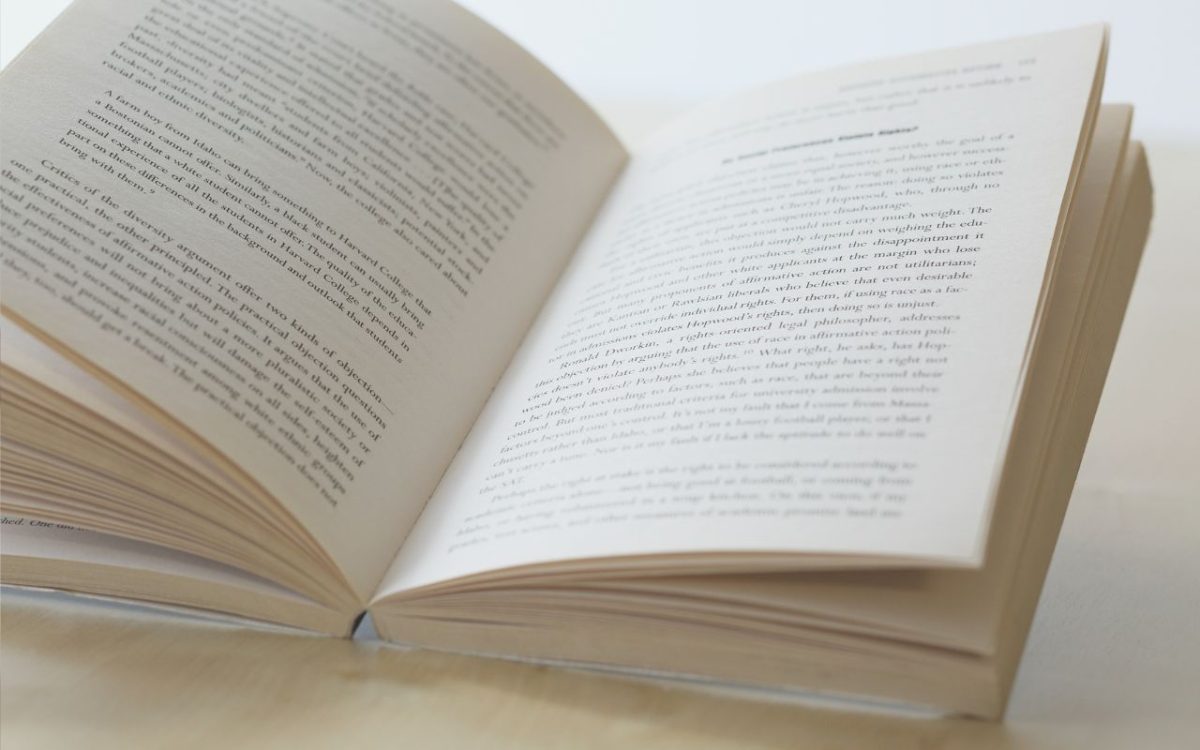
パーパスを導入すること自体が目的化してしまっては本末転倒です。ここでは、パーパス策定前に検討すべきリスクや前提条件を確認しておきましょう。
パーパスの“流行”に乗るリスク
ハーバード・ビジネス・レビューなどでも取り上げられる「パーパスブランディング」ですが、安易にトレンドとして導入することにはリスクもあります。表面的な「正しさ」だけでパーパスを定義すると、社内の共感を得られず、むしろ空虚なスローガンになってしまう可能性があります。
大切なのは、外部評価や時流ではなく、自社の本質から言葉を紡ぎ出すことです。
自社の理念が浸透していない段階では逆効果になる可能性
そもそも経営理念が社内に浸透していない状態で新たに「パーパス」を導入しても、社員は混乱するばかりです。言葉を増やせば伝わるというものではありません。
むしろ、現行の理念を改めて見直し、必要であれば補助線として「パーパス」を追加するという考え方が現実的です。理念とパーパスの“二枚看板”にする場合は、その役割分担と使い分けを明確にしておくべきでしょう。
大手企業と中小企業では導入意義が異なる
パーパスは本来、企業の存在意義を社会と共有するための概念です。大手企業であれば、グローバルなガバナンスやSDGs対応としての意味がありますが、中小企業にとってはそこまで広いスコープを求める必要はありません。むしろ、自社のファンや地域、取引先といった“小さな社会”との関係を再定義する道具としてパーパスを使う方が、実践的かつ効果的です。
まずは理念浸透から
パーパスとは、単なるスローガンではなく、企業が社会に対して果たすべき役割を明確にするための指針です。その定義や導入には慎重さが求められますが、本質を掘り下げることで、経営理念とは異なる視点から企業の姿勢を表すことができます。
ただし、理念が社内に浸透していない段階でパーパスを上書き的に導入しても意味はありません。自社の文化や歴史に根ざした“存在意義”を見つけ、それを言語化することが、これからのブランディングにとって重要な取り組みとなるでしょう。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



