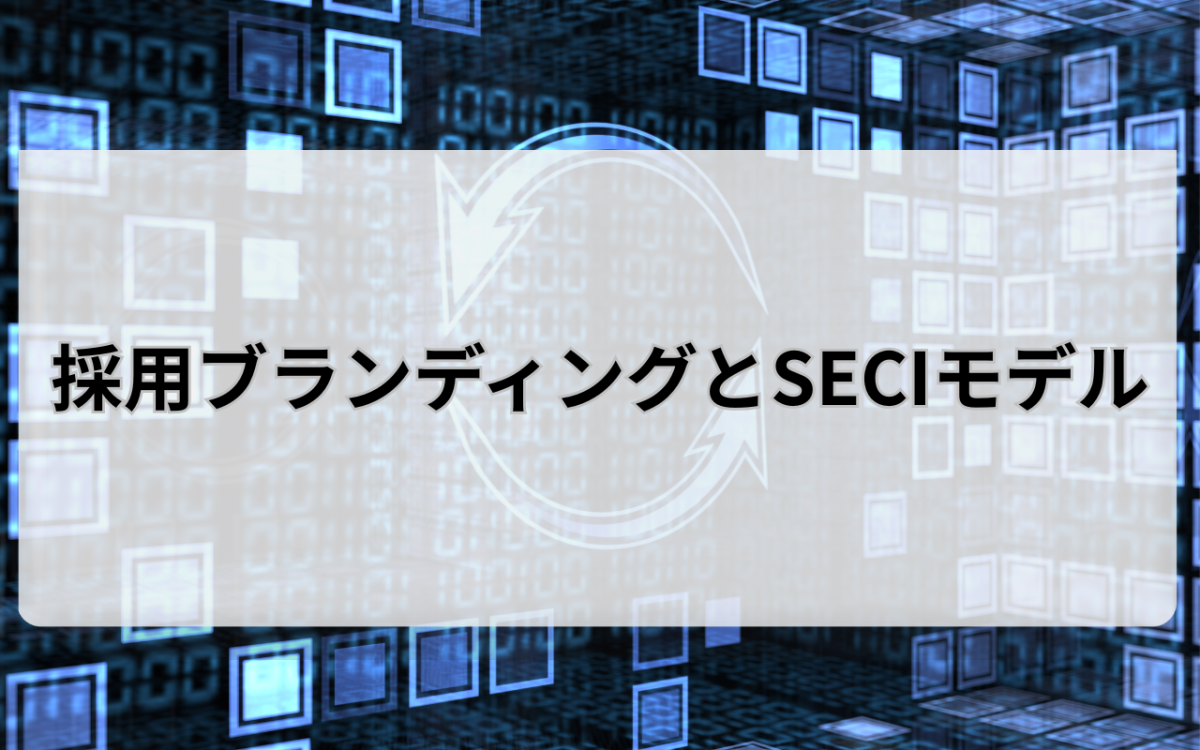
「求職者に自社の魅力が伝わらない」
「理念はあるが言葉になっていない」
「企業の文化が表現できず、ミスマッチが続いている」
こうした悩みは、多くの中小企業やスタートアップが抱える採用課題の根本です。待遇や福利厚生だけでなく、企業としての“あり方”が選ばれる時代。採用において文化を伝えることの重要性が、あらためて見直されています。
しかし、文化や価値観はそもそも“暗黙知”として組織に蓄積されているものであり、それをそのまま伝えることは容易ではありません。
そこで注目されるのが、知識創造理論「SECIモデル」です。
この記事では、採用ブランディングの実務とSECIモデルを結びつけながら、暗黙知を形式知へと変え、文化を伝えられる組織になるための実践的なアプローチを解説していきます。
SECIモデルとは?—知識を共有・変換する4つのプロセス
SECIモデルは、野中郁次郎氏によって提唱された知識創造理論です。暗黙知と形式知の相互変換によって、組織の知識は深化し、新たな価値が生まれるとされています。
このモデルは以下の4段階で構成されます。
- 共同化(Socialization):暗黙知から暗黙知へ。共体験による感覚の共有。
- 表出化(Externalization):暗黙知を形式知へ。言語や図式によって共有可能な形に。
- 連結化(Combination):形式知を形式知へ。複数の形式知を組み合わせ、構造化する。
- 内面化(Internalization):形式知を暗黙知へ。言語化された知識が行動を通じて再び体得される。
このプロセスは円環的に繰り返され、組織の中で知識と文化が深化・進化していきます。
実務に活かすためのポイント:SECIモデルを採用活動にどう落とし込むか

SECIモデルはあくまで理論です。実務に落とし込むには、次のようなステップが有効です。
- 共同化:経営者や現場社員の言動に一貫性を持たせ、求職者との接点で文化を体験させる
- 表出化:採用ブランドを言語化するツールを活用し、理念や価値観を整理する
- 連結化:言語化されたコンセプトを、あらゆる採用コンテンツに反映させる
- 内面化:日常業務の中でブランドに即した行動を評価・フィードバックする文化をつくる
これらを意図的に繰り返すことで、組織に文化が蓄積され、求職者にも伝わりやすくなっていきます。
【共同化(Socialization)】価値観を“感じる”段階
共同化は、言葉になっていない「空気」や「想い」を、職場での体験や行動を通じて共有するフェーズです。経営者が何を大切にしているか、社員がどんな判断をしているか、そうした感覚はまず、日々の仕事の中で体得されていきます。
この段階は、いわば“企業文化”の源泉です。採用ブランディングにおいても、まずはその企業らしさを社員自身が内面化しているかどうかが重要です。もしここが未形成であれば、どれだけ魅力的な言葉を並べても、説得力を持ちません。
【表出化(Externalization)】価値観を“言葉にする”段階
採用ブランドにおける最大のハードルが、この「表出化」です。たとえば、ある企業で大切にされている“挑戦の風土”を、どう言語化するか。どんな表現ならば、自社の価値観を言い当てられるのか。
このプロセスを経ることで、企業の暗黙知が「形式知」になり、採用メッセージの核が形成されていきます。
【連結化(Combination)】言葉を“構造化・共有”する段階
言語化された価値観は、採用ページ、面接の場、パンフレット、動画など、あらゆる接点に落とし込まれます。これが「連結化」です。たとえば、「主体性を尊重する文化」があるなら、その具体的な制度や事例と紐づけて整理する。
この段階では、採用チームだけでなく広報や現場メンバーとの連携が重要になります。一貫性をもって構造化・共有されることで、応募者との接点における説得力が高まり、候補者の「共感」や「納得」につながります。
【内面化(Internalization)】文化が“根づく”段階
最後のプロセスは、形式知として伝えたものが、再び社員個人の行動原理として定着する段階です。たとえば、新しく入社した人が、採用時に聞いた言葉通りの文化を実際に感じ、「この会社に入って良かった」と納得する瞬間。
これは、採用ブランドが“実態”と一致していた証拠であり、文化の循環がうまく回っている企業の姿です。内面化が進むことで、さらにその社員が新たな文化の担い手となり、次のSECIサイクルが始まります。
採用ブランディングは“知の循環”で育つ
SECIモデルを活用すれば、採用ブランドは単なる「スローガン」ではなく、組織の“知”として循環し続ける存在になります。採用ブランディングとは、表面的なキャッチコピーではなく、組織の内と外をつなぐ「本質の共有」に他なりません。
そしてその本質とは、暗黙知として眠っている社員一人ひとりの体験や感覚を、言葉に変え、形にし、また新たな行動へと昇華させていく営みです。
文化は“伝わってこそ”文化になる
採用ブランディングの本質は、「自社らしさをどう伝えるか」にあります。SECIモデルの視点から見れば、そのプロセスは知識や価値観の転換と定着であり、決して一朝一夕でできるものではありません。
しかし、まずは表出化=言語化から始めれば、採用だけでなく組織全体の一貫性が生まれ、文化の再構築にもつながります。経営者や採用担当者が自社の言葉を見直すきっかけとして、SECIモデルの枠組みは非常に実践的なツールになるのです。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



