
チームビルディングにおけるインナーブランディングの価値を理解したなら、次に必要なのは「どう実践するか」です。
この記事では、信頼関係の構築、対話の仕掛けづくり、ロールモデルの育成、そして従業員の納得感を高めるインナーブランディングの実践的視点を紹介します。
共通の価値観が信頼関係をつくる
信頼は偶然には生まれません。背景には必ず、共通の考え方や目的意識が存在しています。
以下では、インナーブランディングを通じて信頼を育む構造を紐解きます。
「共感してここにいる」という安心感
社員同士の相性はそれぞれ異なります。しかし、同じ企業に在籍しているという事実が「同じ価値観に共感している仲間である」という共通認識を生み出せば、信頼関係は築きやすくなります。
これは、個人対個人の関係に留まらず、組織全体に波及していきます。
全体に広がる信頼のネットワーク
理念という共通項があることは、個人間の関係構築ではなく、組織全体との結びつきを強くします。
特定のAさんとBさんだけの関係ではなく、A・B・C・Dとメンバー間に横断的に信頼が築かれていくのです。
共通項があるからこそ、安心して意見を交わし、支え合う文化が根づいていきます。
対話を生むには、仕組みも必要
共通項があっても、自然と対話が生まれるとは限りません。
だからこそ、意図的に「対話のきっかけとなる場」を設計することが求められます。
インフォーマルな時間を制度にする
「飲みにケーション」が難しい現代においては、業務時間内にインフォーマルな対話の場をつくることが現実的です。たとえば、共通の価値観をテーマにした短時間のグループトーク、部署間シャッフルランチ、アイデア交換会など。
こうした時間が、自由で率直な対話を後押しします。
自由な関係性を育む小さな工夫
仕掛けは小さくても構いません。自販機の利用に社員証が使えるようにするといった工夫も、共通の仕組みを通じた接点になります。
ランチ制度、部活動の推奨なども含め、社内に偶発的な会話が生まれる導線を増やしていくことが効果的です。
ロールモデルは決めるのではなく、育てていく
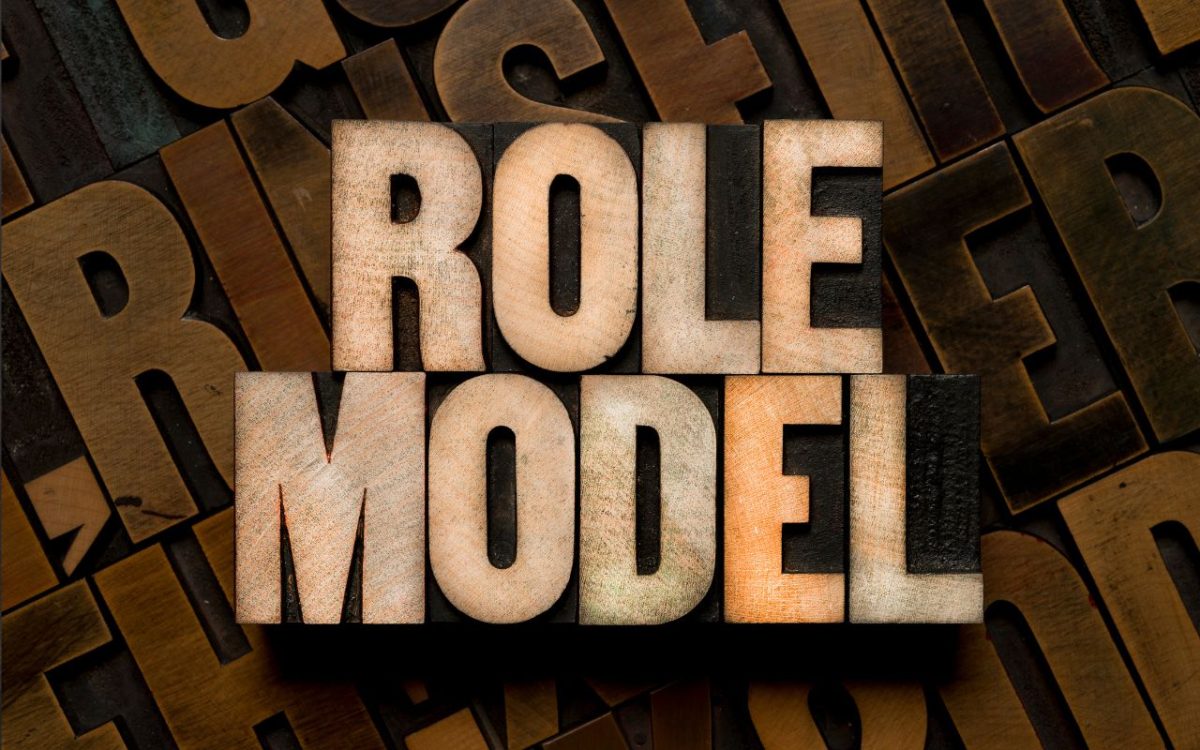
ロールモデルをあらかじめ「この人です」と定める必要はありません。大切なのは、行動が現れたタイミングで称賛し、それをチームで共有する仕組みを持つことです。
MVP文化が模範を育てる
「この行動は素晴らしい」と具体的にフィードバックし、MVPとして社内報やミーティングで紹介する。そんなサイクルがあれば、自然と「私もやってみよう」と思える文化が醸成されます。
完璧なお手本はいませんが、「今できていること」を認めることは誰にでもできます。
一番のロールモデルは経営者自身
「うちの会社で大事にしたいことは、私自身が一番大事にしている」。その姿勢をトップが見せることが、最も強いメッセージになります。
できていない自分を見せることも、むしろリアルで信頼を生みます。
自分のためにもなると思えるかどうか
どれほど素晴らしい理念であっても、それを「自分ごと」として捉えられなければ行動は続きません。重要なのは、「これを大切にすると、自分の人生にもプラスになる」と思える納得感です。
行動が報われる論理をつくる
理念の実践が評価に繋がる、あるいは承認される。そんな構造が整えば、社員は「やってよかった」と思えます。
「自分のためでもある」と思える論理が整うことで、行動の継続が可能になります。
未完成でも進もうとする姿勢が、強いチームを育てる
インナーブランディングに完成形はありません。理念をどう解釈し、行動に変えていくかは、個人も組織も日々の試行錯誤の中にあります。
だからこそ、「完璧ではないけれど、今日より明日を良くしていこう」という姿勢こそが、チームビルディングの本質です。
むすびでは、企業ごとの風土に合わせた実践支援を行っています。価値観の共通化から制度設計、称賛文化の醸成まで、どこからでも始められます。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



