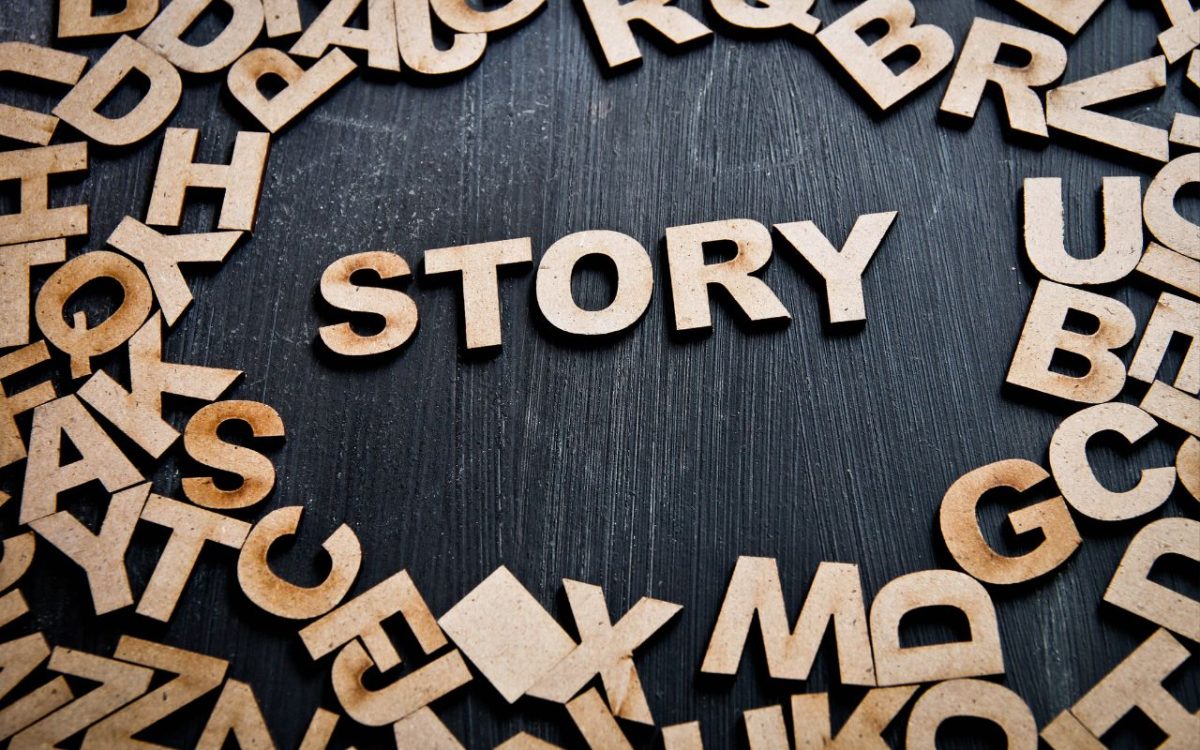
採用市場は年々変化し、単なる給与や待遇の条件提示だけでは人材を惹きつけられない時代になりました。求職者は企業の理念だけでなく、「実際にどんな挑戦ができるのか」「どんな仲間と働くのか」といったリアルなストーリーに共感し、志望意欲を高めています。そうした背景から注目されているのが、プロジェクトストーリーの活用です。
本記事では、採用活動におけるプロジェクトストーリーの重要性と、その効果を最大化するために不可欠なインナーブランディングの視点について詳しく解説します。
なぜ今、採用活動にプロジェクトストーリーが求められているのか
単なる条件提示ではなく、リアルな経験や挑戦のストーリーが求職者の心を動かす時代です。
以下でその背景と理由を整理します。
企業理念や条件だけでは伝わらない時代になった
給与や福利厚生だけでは、求職者の心に響かない時代になっています。なぜなら、多くの企業が同じような条件を提示しているため、差別化が難しくなっているからです。
求職者は「ここで働く意味」を探しており、それを伝えるためには、企業が実際に取り組んだ挑戦や葛藤、成長の過程といった具体的なストーリーが欠かせません。
求職者は「リアルな経験談」から会社を見ている
企業公式サイトや求人票では見えない部分、つまり「実際にどんなプロジェクトがあるのか」「どんな苦労があり、それをどう乗り越えたか」といったリアルな経験談こそ、求職者の関心を集めます。
入社後のイメージが明確になればなるほど、ミスマッチも減り、採用活動の質が向上します。
ストーリーは“入社後の未来”を具体的に想起させる
単なる条件や理念だけでは、入社後の自分を具体的にイメージするのは難しいものです。プロジェクトストーリーを通じて「自分もこんな挑戦ができるかもしれない」という未来像を描かせることができれば、志望動機は格段に強まります。
これは採用活動において大きな武器となります。
採用におけるプロジェクトストーリーとは何か?
プロジェクトストーリーは単なる成功体験の披露ではありません。以下でその本質と、採用活動への活用法を解説します。
具体的な挑戦や葛藤を描くことで共感を呼ぶ
プロジェクトストーリーとは、あるプロジェクトの成功体験だけでなく、そこに至るまでの挑戦、葛藤、失敗、工夫などの「過程」をリアルに描くものです。
華やかな成果だけではなく、苦労したポイントや乗り越えた工夫を描くことで、求職者の共感を引き出すことができます。共感は志望意欲に直結します。
成果だけでなく“過程”にこそ魅力が宿る
よくある失敗は、成果だけを強調してしまうことです。しかし、求職者が知りたいのは「この会社に入ったら、自分はどんな過程を経験できるのか」という点です。
成功までの苦労や努力のストーリーこそが、会社の本質や文化を映し出し、求職者に「ここで成長できそうだ」と感じさせる要素になります。
現場視点のストーリーは、企業文化を伝える強力なツール
プロジェクトストーリーは、経営層の理念ではなく、現場で働く社員一人ひとりの視点から語られることで、よりリアルな企業文化を伝える力を持ちます。
たとえば、若手がリーダーを任され苦労したエピソードや、部署横断で助け合った経験などは、チームワークや挑戦文化といった「空気感」を求職者に伝えるうえで非常に有効です。
プロジェクトストーリーを機能させるには、インナーブランディングが必要
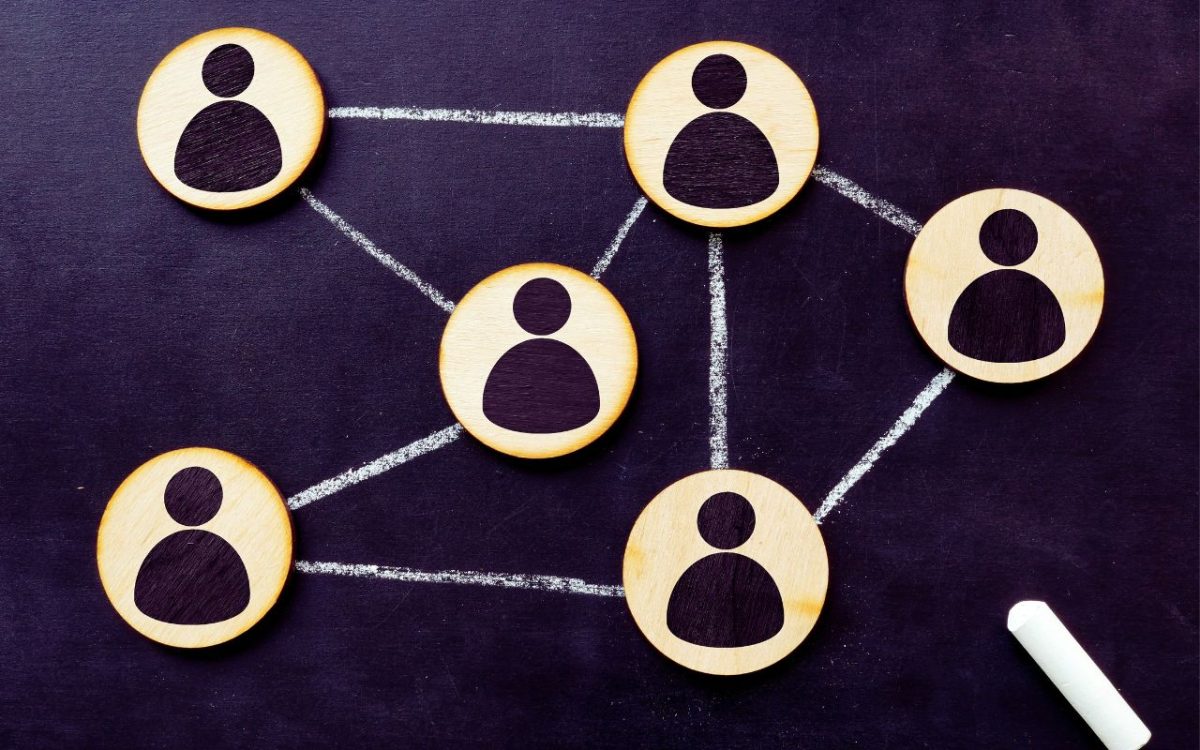
どんなに良いストーリーを作っても、価値観が社内でバラバラではメッセージに一貫性が出ず、逆効果になってしまいます。以下でその理由と対策を解説します。
バラバラの価値観では、ストーリーに一貫性が出ない
部署ごとに異なる価値観を持っていると、発信されるストーリーもバラバラになってしまい、求職者に混乱を与えます。
「この会社は何を大切にしているのか」という軸が伝わらなければ、魅力は半減します。だからこそ、ストーリーを語る前提として、価値観を社内で統一しておく必要があります。
“誰が語っても同じ軸”を持たせるための価値観共有
採用広報においては、経営層、現場社員、採用担当者それぞれが語る言葉に一定の共通軸が必要です。そのためには、企業としての「採用観」「仕事観」「人材観」を明文化し、日常的に共有する文化を育てることが欠かせません。
これがインナーブランディングの基本です。
現場メンバーのストーリー発信力も育成する
インナーブランディングが浸透すれば、現場社員一人ひとりが自分たちの言葉で自然にストーリーを語れるようになります。
特別な広報素材を用意しなくても、日常的な取り組みやプロジェクト経験を魅力的なストーリーとして発信できる組織は、採用力が格段に高まります。
採用プロジェクトストーリーが、企業の未来をつくる
プロジェクトストーリーは単なる採用手法ではありません。それは、企業文化を言語化し、内外に発信する重要なブランディング活動でもあります。リアルな挑戦や成長の過程を共有できる企業には、共感した人材が集まります。そしてその共感は、入社後の定着率やエンゲージメントにも直結します。
採用のためにストーリーを磨くのではなく、日常の中にストーリーが息づく文化を育むこと。インナーブランディングを通じた価値観共有こそが、これからの採用力を根本から高める鍵になるのです。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



