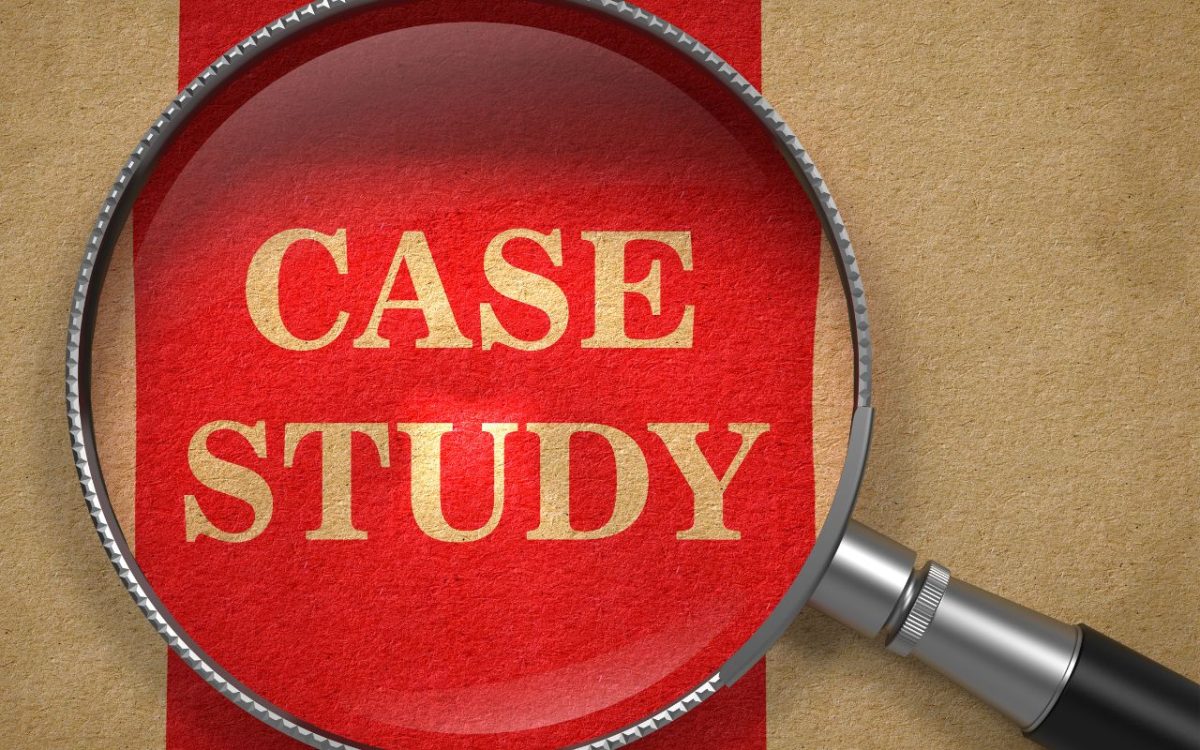
採用市場が大きく変化する中で、応募者の価値観や思考を深く知るための手法が求められています。条件や経歴だけでは測れない「その人らしさ」をどう見抜くか。
そのヒントとなるのが、採用プロセスへのケーススタディ導入です。この記事では、採用におけるケーススタディの意義、活用方法、そして他社との差別化を生む価値について解説します。
ケーススタディがもたらす6つの価値
以下で、ケーススタディを採用活動に取り入れることで得られる具体的な価値について紹介します。
1. 【行動・思考】応募者の“思考力と価値観”が見える
通常の面接では見抜きにくい「考え方のクセ」や「判断の背景」が、ケーススタディでは浮き彫りになります。たとえば「新店舗立ち上げ時の人員配置をどうするか」といった問いかけに対する回答から、その人の優先順位やコミュニケーションスタイルが明らかになります。
2. 【育成】研修・教育にも転用できる
採用時のケーススタディは、そのまま入社後の研修コンテンツとしても活用可能です。実在する自社の事例を使うことで、早い段階で仕事の全体像や価値観を伝えられます。
3. 【ブランド】独自の採用体験がつくれる
ケーススタディは、応募者にとって「この会社、他とは違うな」と感じる印象的な体験になります。「問題を一緒に考える」プロセス自体が、企業のブランドを強く印象づける要素になるのです。
4. 【共感】読後フィードバックで“理念共有”が起きる
ケーススタディ後のディスカッションやフィードバックを通じて、企業理念への理解が深まります。「なぜこの判断をしたのか?」という会話を通じて、価値観の一致・不一致も確認しやすくなります。
5. 【効率】採用フローの説明・面接時間が短縮できる
よくある質問への対応をケース内で網羅できれば、採用フロー内の説明時間を短縮できます。また、応募者からの理解度が上がるため、面接の質も向上します。
6. 【独自性】他社にはない“企業知の教材化”ができる
社内でしか語られていなかった知識や判断基準が、ケーススタディという形で言語化・教材化されます。これは、企業の知見を蓄積・活用するナレッジマネジメントの一環でもあります。
ケーススタディの活用シーンと利点
ケーススタディの活用シーンは多様です。特別に「こういった状況でなければ使えない」というものではありません。
たとえば、以下の
- インターン
- 会社説明会
- 一次面接〜二次面接の間
- 内定者フォロー
- 内定者研修
どのフェーズでも柔軟に使えるのがケーススタディの強みです。「話す」だけではなく「考える」「感じる」「発表する」プロセスがあることで、より深い会社理解が得られます。
ケーススタディは「設計できる会社」にしかつくれない

効果的なケーススタディを設計するには、そもそも企業側に「自社の思考・判断軸を言語化する力」が必要です。何を問うか、どんな情報を与えるか、どういうフィードバックをするか。これらすべてに、会社の思想や価値観がにじみ出ます。
さらに、「ケースにどこまで会社側の情報を含めるか」もポイントです。応募者のヒントになるような情報をあえて散りばめることで、より深い対話が可能になります。
テーマ設定の工夫が、問いの質を左右する
たとえば以下のようなテーマが、ケーススタディとして活用されています。
- 「新卒採用を初めて実施する際の社内巻き込み」
- 「地方支店で新たに店舗を立ち上げるときの課題」
- 「若手社員を最年少で課長にする際の判断基準」
ポイントは、“正解・不正解がない問い”であること。企業として「こういうときにどう考えるのか」という思考のプロセスを伝えることが、最大の目的です。
ケーススタディで「採用できる会社」がわかる理由
実は、良質なケーススタディを設計できる会社は、それ自体が“採用力のある会社”の証です。なぜなら、以下の要素がすでに整っているからです。
- 判断の背景となる理念・思想が明文化されている
- 社内で共有された価値観が存在する
- 応募者と真剣に向き合いたいという文化がある
また、AIや外注では作れない「現場の知」が必要とされるため、手作り感やリアルさが応募者に伝わります。それは、企業ブランディングとしても強力な武器になるのです。
採用活動の中に“学び”を埋め込む
ケーススタディの導入は、単なる選考手法ではありません。応募者にとっても企業にとっても「価値ある学びの場」であり、「未来の仲間と考える第一歩」です。
問いの設計、フィードバック、対話。これらを丁寧に積み上げていくことで、採用活動は単なるスクリーニングから、理念共感のプロセスへと進化します。自社なりのケーススタディをつくり上げること。それが、これからの時代の採用ブランディングを支える鍵になります。
むすびでは、これらのケーススタディの作成サポートもリリースを予定しています。
「採用ブランディングで全体を設計するための時間や費用の捻出が難しい」
上記のようにお悩みの企業は、ぜひケーススタディの作成もご検討ください。
詳しくはお問合せください。

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)



